
情報主任って、いったいどんな仕事をするの?
小学校でこの役職に任命されたとき、多くの若手教員が感じるのは不安です。ICTが苦手、機械に強くない、経験がない……
しかも、GIGAスクール構想が始まって数年経ち、先生方もタブレットの使い方を分かってきていて、自分なんかにできるのかと不安になりますよね……
「いきなり年度更新?」「学習アプリの設定?」「ホームページ更新って、どうやるの?」
年度末と年度初めは業務が山積みで、ひとりで抱え込むと心が折れそうになります。
でも大丈夫!
この記事では、現役の小学校教員であり、20代で4年間情報の担当を務めた夫の実体験をもとに、仕事内容やコツ、気をつけたいポイントを丁寧に解説します。
読み終える頃には、情報主任の全体像がつかめて、「自分にもできそう」と思えるはず。この記事は、特に次のような人におすすめです。
- 情報主任を任されたけど何から始めていいかわからない人
- 小学校のICT関係の役職について知りたい人
- 若手教員でも安心してできる情報主任の工夫を知りたい人
それでは早速見ていきましょう!
この記事を書いた人
情報主任 小学校の主な仕事9つとは?
① 学習アプリ・アカウントの管理
Googleアカウント、デジタル教科書、プログラミング教材、ドリル教材…。
児童も教員も、さまざまなオンラインサービスのIDやパスワードをもっています。
児童も教員もいろいろな人がパスワードを忘れたり間違えたりします。その時に助けてあげるのも情報主任の仕事です。
また、年度が替わると転任者や転入生がいて作成・更新・削除しなければなりません。
学年が変わるタイミングで、各サービスのデータ整理や新年度用のアカウント準備が一気にやってきます。
各サービスごとにページが違い、管理ページなどは日常的に触るものではないので、混乱することも多々あります。
また、事前に前任者にやり方を聞いていても、聞くだけではやはり分からないことが多くあります。
初めて情報主任をされる方は、とにかく「早く触ってみる」ということを心がけましょう
② 学校ホームページの更新と作成
「お知らせ」「年間行事予定」「学校だより」などのページを定期的に更新するのも情報主任がする仕事の一つです。
保護者や地域にとっての“学校の顔”でもあるため、誤字脱字チェックや写真の掲載マナーにも注意が必要です。
こちらもマニュアルはあることが多いですが、触ってみないと分からないことが多々あります。
ホームページにのせるもの自体は、ほかの先生が作ったものをのせることが多いので、
- 早く触って分からないところを見つけること
- 「ホームページにのせるから作ったらデータをくださいね」という依頼
この2点だけは早めに伝えておきましょう。
③ 端末や周辺機器の管理・設定
インターネット上の管理だけではなく、端末などの「もの」を管理するのも情報主任の仕事です。
今の学校現場には様々な機器があふれています。
- 一人一台のタブレット
- 教員用PC
- プリンターやWi-Fi、LANケーブル
- カメラ、提示装置などのICT機器
これらのトラブル対応や使い方の説明も情報主任の仕事です。
端末の充電・持ち帰りルールの周知、棚の整理など、細かい業務も多いですが、タブレットをたくさん使ってもらいたいなら、こちらの仕事は欠かせません。
④ 情報教育の年間計画づくり
学年ごとに「どの時期に、どのICTスキルを教えるか」をまとめた情報教育の年間指導計画を立てます。
たとえば:
- 1年:タブレットの持ち方とログインの仕方
- 3年:写真や動画を使った学習
- 5年:表計算・プレゼンの作成
といった具合に、発達段階に合った内容でスモールステップを意識します。これは他の先生方の授業準備や教材研究などにも役立ちます。
⑤先生方への研修や情報提供の工夫
タブレット活用法を先生に伝える
どんなに便利なICTツールがあっても、「使い方がわからない」「めんどくさい」と思われては意味がありません。
情報主任は、簡単にできる活用例やテンプレート、ほかの先生方の利用法などを他の先生方に紹介するのがとても大事。
「ここを押せばOK」「5分で終わる」など、忙しい先生たちの目線での共有が喜ばれます。
研修の開催タイミングと内容の工夫
学期始めや職員会議だけでなく、5〜10分のミニ研修を挟むのもおすすめ。
無理のないタイミングで、「ちょっと便利になる」「ショートカットキーの使い方」など内容に絞ると利用率もアップします。
例:
- 「コピー&ペーストのショートカットキー」
- 「canvaやkahootでクイズを出す方法」
- 「共有フォルダの作り方」
⑥チャイム設定のコツと注意点
意外と知られていない情報主任の仕事がチャイムの時刻設定や調整。
情報主任が放送主任を兼ねることが多いので、任されることもあります。
大体の学校は情報主任(放送主任)か教務主任がしていると聞いています。
行事や下校時刻の変更に応じて特別時程の音を鳴らす設定やチャイムが鳴らないような設定も行います。
特に健康診断の時期や行事が多くある時期は要注意。
職員会議で決まった予定をもとに作成し、担当者に確認してもらってから設定するとスムーズ
⑦多すぎる調査依頼、どうこなす?
「〇〇アンケートを集計してください」「ICT機器の使用状況を教えてください」など、各方面からの調査依頼も山ほど来ます。
同じ内容を何度も答えることもあるので、「情報機器についてはここ」「使用頻度についてはここ」などフォルダをしっかりと整理しておくことも重要です。
年度末には国からの調査も来ますので、それについては前年度のデータがどこにあるかもしっかりと確認しておきましょう。
また、最近は学校から保護者へのアンケートもネットで行うことも多いです。その時にはQRコードを作ったり、質問のページを担当者と一緒に作ったりしましょう。
⑧小学校の相談役としての立ち回り
正直、情報主任の仕事としての大半がこれになります。
教材研究等、授業のことならまず自分で考えたり調べたりするのに、パソコンのことになると、調べる前に聞いてくることも多いそうです。
先生方の「困った」にどう対応?
「パソコンが固まった」「音が出ない」「配布資料が印刷できない」……
そんな時、先生たちがまず相談するのが情報主任。
相手を否定せずに、まずは一緒に確認する姿勢をもつことが大切。感謝されることも多く、職員室内での信頼構築にもつながります。
どうしても今は無理というときにはしっかりと事情を説明し、いつならできるかを伝えるのも大切です。
わかりやすい説明のコツ
ICTに苦手意識がある先生も多いため、専門用語はなるべく使わず、
「このボタンを押すとこうなります」「この説明資料の赤い文字のところだけはしてください」など、具体的で視覚的な説明が効果的です。
覚えておいてほしい仕組みやポイントだけはしっかりと説明するとよいでしょう。
⑨ 情報教育の推進
情報主任として、学校全体での情報教育の方向性を示すことも大切な役割です。
情報教育とは、単にタブレットの操作方法を教えるだけではありません。
児童の情報活用能力を育てることが目的です。
そのためには、学級担任任せにせず、学校全体としてどのようにICTを活用していくか、また情報モラル教育をどう位置づけるかを考える必要があります。
たとえば:
- 各学年の発達段階に合わせた情報モラル教材を提案する
- 端末を上手に活用している事例を紹介し、推進する
- 校内に「ICT活用掲示板」や「簡単にできるICTの紹介コーナー」などを設け、情報共有を促す
といった工夫も有効です。
情報主任は、「教える側」の先生たちが迷わずICTを活用できるようにサポートしながら、子どもたちの“情報とのかかわり方”や”端末の正しい使い方”を学校全体で育てていく舵取り役です。
年度末と年度初めは情報主任の繁忙期
情報主任の中でもっとも忙しい時期は、やはり年度の切り替えです。
上記の仕事①②③④⑥⑦⑧を短期間で行わなければいけません。さらにこの仕事たちは時間も手間もかかるのに、年度初めは時間もあまりありません。
素早く計画的に取り組むことが大切です。
なぜこれが大変なのかというと、各サービスによって操作方法やルールが異なるからです。しかも、すべてを一人で管理する学校も多く、年度の切り替えに追われてしまいます。
- 事前にマニュアルを見たり前任の先生に聞いたりしておく
- やらないといけない順番を整理し、1つずつ取り組む
- 他の先生に名簿を準備してもらうなどしてもらえるところはお願いする
まとめ|情報主任の仕事は「やればできる」に変わる!
情報主任の仕事は、確かにやることが多く、専門的に感じる部分もあります。
でも、やってみると「意外となんとかなる」ことばかり。特に、前もって流れやコツをつかんでおけば、不安はグッと減ります。
最初はうまくいかなくても大丈夫。
周りの先生に助けてもらいながら、少しずつ慣れていけばいいのです。
あなたのちょっとしたサポートが、学校全体のICT活用をぐんと進めることになります。
「できることから一つずつ」
その気持ちがあれば、情報主任としてしっかり活躍できますよ!
そのほかの校務分掌についてもちょっと知りたい!という方は以下のリンクから覗いてみてください!
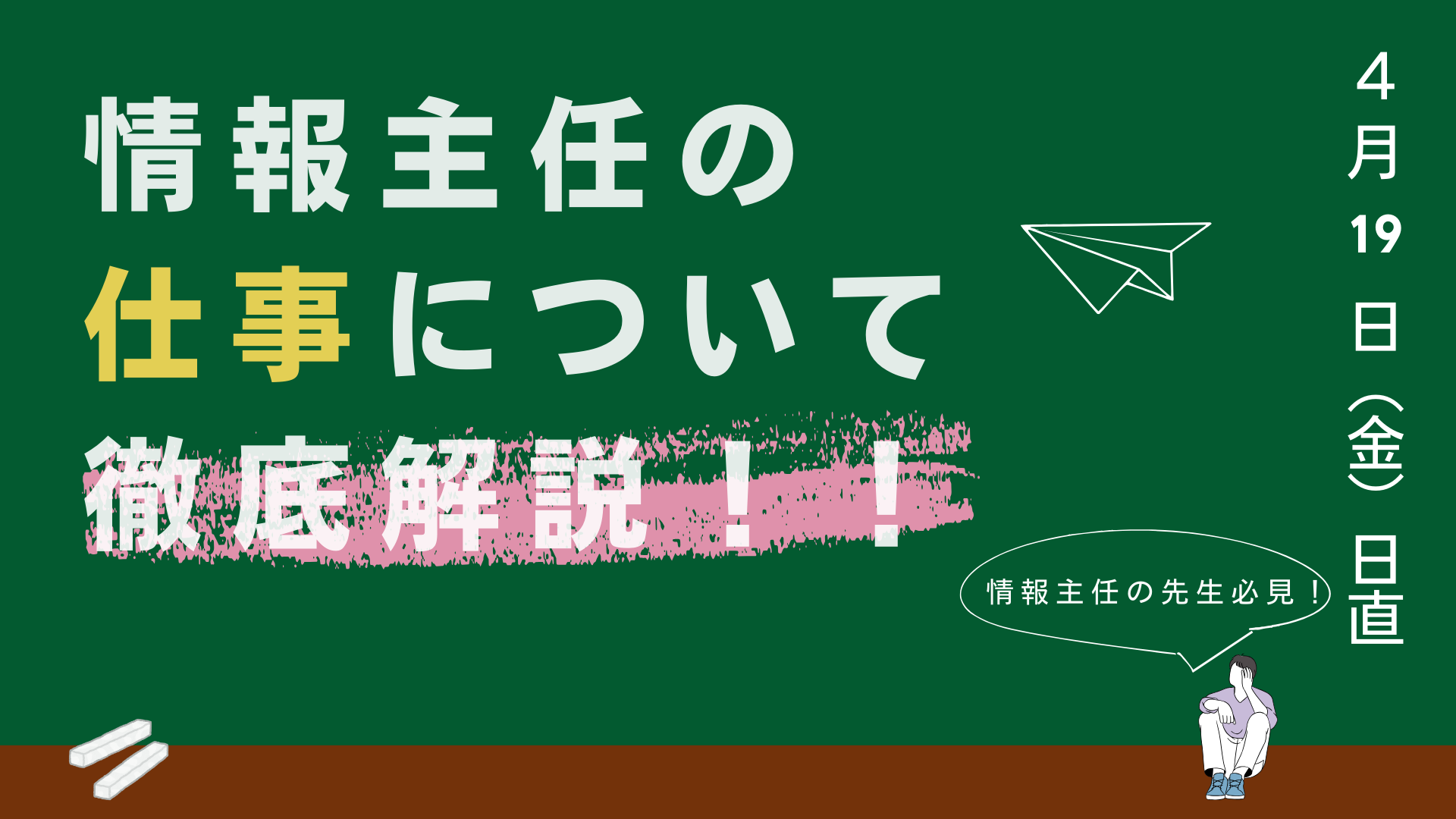
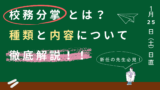


コメント